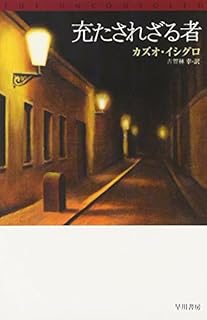ノーベル文学賞を受賞した、日系イギリス人の、カズオ・イシグロさん。
すでに何年も前から、文学好きの間では結構な評判になっていて、私も「日の名残り」と「私を離さないで」は、仲間から回ってきて読みました。
この機会に、他のも読んでみようと思います。
そんなわけで、内容紹介もしつつ、今すでに日本語に訳されている、カズオイシグロの小説や本の一覧を作ってみます!
それぞれ好みは違うと思いますので、この中から、ご自分が興味引かれたのを選ぶ参考になれば嬉しいです☆
※ 書影はAmazonより拝借。
【目次】
「遠い山なみの光」
- 原題:A Pale View of Hills
- 出版:1982年
あらすじ
悦子は、日本でジローという男性と結婚し、景子という子供を授かっていた。だがその後、イギリス人男性と出会い、彼と、娘の景子と一緒に渡英してきた。
二番目の夫との間に生まれた娘が、ニキである。ニキが生まれた時、悦子は「何かモダンな名前がいいな」といったが、夫は「東洋的な響きを持つ名前がいい」といった。その結果、妥協の産物として「ニキ」という名前を付けたのだった。
イギリスに来てから、だんだん景子は孤独で、引きこもりがちになってしまう。部屋からは、夕飯の皿を取りに来るときしか出てこない。そしてついに自殺してしまったのだった。
悦子は、日本にサチコという友達がいた。サチコには、マリコという娘がいて、彼女も、ひどく孤独で引きこもりがちな少女だった。悦子は、サチコは、娘マリコと、フランクという日本に大戦後駐在していたアメリカ兵と一緒に、合衆国に渡ろうと計画していたのを思い出すのだった。
サチコの人生の物語と、悦子のそれは、確かに似ているのだった・・。悦子の回想により物語は進められる・・・。
読んだ人の感想
Amazonのブックレビューから、読んだ人の口コミを幾つかピックアップします。
原作を読むと、終盤に衝撃的なストーリーの転換があります。 日本語版は最後まで淡々とした描写で終わっていきます。 全く趣の異なる本になってしまっています。 これは翻訳者のミスです。 日本語訳版しか読んでいない方は、ぜひ原書を読んで下さい。全くの別物です。 この日本語訳版の問題については著者もインタビューで語っています。
本書はカズオ・イシグロの処女長編だが、本書からすでにカズオ・イシグロの長編小説のスタイルが確立されていたことがよくわかる。
ほかのカズオ・イシグロの長編と同じく、本書も語り手の回想と追憶によって綴られる物語である。本書は私を含めた一般的な読者が知りたいと思われる情報は、実は、直接に語り手は語ってない。なぜ語り手である悦子は離婚したのか、なぜイギリスに在住しているのか、なぜ景子は自殺を選んだのか。ページを読み落としたのか?
と思えるぐらいに。(数行、触れているところはある)ただし、長崎での佐知子と万里子との交流、語り手の義父である「緒方さん」と夫、ならびにかつての教え子のすれ違い・・・数々の回想から、その背景について、読者に類推を迫っている。
米兵とともにアメリカに渡った後の生活を夢として語る佐知子と、夫と子供と共にある自身の生活は幸せだと語る悦子、二人の会話が完全にすれ違っている場面は一つの山場だと思いました。(略)同時に女性が自分らしく生きることの難しさを感じさせる展開でした。
ちょっと、翻訳に問題があるという意見もありましたので、読める人は英語で読むのがいいかもしれません。日本から英語圏への移住をモチーフにしていて、イシグロ氏自身の人生とも深く通じるものがありそうです。
「浮世の画家」
- 原題:An Artist of the Floating World
- 出版:1986年
あらすじ
第二次世界大戦の前夜、日本の画家、小野は芸術的理想を追求しようとする師匠と別れ、極右の芸術組織に参加してしまうようになる。内務省の文化委員会の一員として、小野は警察への密告者となり、イデオロギー的な魔女狩り行為を行った。
1945年の日本の敗戦以降、小野は仲間を密告した「裏切者」として見なされる。
物語の最初の三章では、小野は戦時中に自分がした「過ち」を次第に認めつつあるように描かれている。だが、彼が自分の過ちを本当に認めているのかどうかは、ハッキリとは分からない。そして、最後には彼はまた、戦時中に自分がしたことは間違っていないという方向に戻ってしまう。自分のものの見方を変えることが、ついに出来ないのである。
小野が、自分で作り上げている自己像は、たぶん読者がそれを読んで感じる人物像とはかけ離れたものになる。小野が、自分で自分を欺いてることが、読者には伝わってくるのだ。
読んだ人の感想
この小説は、どこか、小津安二郎の映画の雰囲気に似ているな、と読みながら思った。実際、訳者あとがきによると、カズオ・イシグロが日本を舞台にした小説を書くときに思い出すのは、幼いころの記憶と小津安二郎の作品だという。それにしても、抑制の効いた静かな文体を駆使して丁寧に人々を描くこの作者の力量は見事というしかない。大変優れた作品である。
人生の終わり近くに至って、自分の生き方(の少なくとも一部)が間違っていた(ようだ)と気づかされた老人が過去を振り返るという構造は『日の名残』と重なる(執筆されたのは本作が先だが)。
主人公Ono(訳では「小野」)の述懐はしばしば脇道に逸れ行きつ戻りつするし(作為的なものだろう)、しかもその回想に偏りや偽りがあることは容易に想像できるから「行間を読む」作業が必要になる。そういう点で謎解きに似たスリルがある。
ただ、舞台が第二次世界大戦後の日本ということもあって、つい「文化人の戦争責任」といった言葉が脳裏をかすめて『日の名残』のように物語を純粋に味わうことができなかった。
『日の名残り』でも同じなのですが、主人公は絶えず過去の自分の行動を正当化するので、読者は主人公の語る “事実” につねに疑いを持たざるをえません。なおかつ物語全体を通して主人公の回想という形式がとられています。したがって読者は語り手である「私」を、信用できない “ふたしかな” 人物として、都合の悪い記憶を忘却あるいは改ざんする人物として読み取ります。
そのように書くと主人公が嫌なやつにしか思えないかもしれません。けれど言い訳がましい「私」と良心の呵責に悩む「私」を織り交ぜて主人公の葛藤が描かれているため、読者は思わず主人公に共感してしまいます。そこにイシグロのうまさがあります。
第二次世界大戦時に、自分がしてしまった過ちを、葛藤しながら回想する、という「日の名残り」と同じスタイルが使われているようです。物語の語り手自体が言っていることが、信用ならない状態で読み進めるというのは、なかなかに新しい読書体験になって面白そう!
それに、日本の第二次世界大戦時について興味ある人にもいいですね。「東京物語」で有名な映画監督、小津安二郎を思わせる、静かな日本の風景、というのも注目ポイントです。
「日の名残り」
- 原題:The Remains of the Day
- 出版:1989年
あらすじ
主人公は、年老いた執事スティーブンスだ。彼の回想でこの話は物語られる。
スティーブンスは、ある日、同じお屋敷で働いていたミス・ケントンからの手紙を受け取る。その手紙でケントン婦人は、自分のうまくいっていない結婚生活について、そことなく匂わせているのだった。
ちょうど、現在の雇い主である、リッチなアメリカ人はスティーブンスに屋敷の自動車で、休暇旅行に出かけていいと、すすめてくれているところだった。そこでスティーブンスはこの機会を利用して、デボンに住んでいる、ミス・ケントンに会いに行くのだった。
彼はその道々、回想を巡らす。以前の主人、ダーリントン卿が、第二次大戦前夜に、外交関係に影響を及ぼそうとして、ドイツ人の同調勢力と、イギリスの貴族を招いて交流の場を設けていたこと、それに、偉大なる執事とはどんなものか、、など。
それから、自分のプライベートなこと、父親との関係やミス・ケントンとの間にかつてあった淡い恋愛関係も思い出されてくる。だが、二人は自分たちが感じている愛情を互いに伝えることができなかった。特に、ミス・ケントンが、スティーブンスに積極的に接近しようとしている時も、彼は執事としての職業的立場を優先してしまったのだった。
そして、ダーリントン卿が、献身的に使えるにふさわしいような人物だったかどうかも、次第に疑われてくるのだった・・・。
読んだ人の感想
内容は別の方に譲り、素晴らしい翻訳についてレビューしようと思います。
原著のストーリーの良さもさることながら、素晴らしい訳者様のおかげで良質の日本語小説となっています。
(略)
例えとして冒頭の一部分抜粋します。
(日本語)
ご想像のとおり、あの日、私はファラディ様のお申し出を真剣には受け止めませんでした。なんと申しましてもアメリカの方ですから、イギリスで普通に行われていることと、そうでないことの区別を、まだよくご存じではありません。不慣れゆえのご発言であろうと、その程度に考えておりました。
AmazonのCEOが心に残る一冊に上げていたので読んでみたけど、一流の人は一流の文学を読んでいるんだなぁ。。。
登場人物たちの微妙な心の揺れをとらえた緻密な描写。2つの世界大戦と館での出来事。かつて執事であった父親。多くの使用人たち。出入りする人々。プロフェッショナリズム。ミス・ケイトンとのやりとり。作品を貫く品格。よく錬られた構成。美しい夕暮れ。
面白いとか、エキサイティングだとか、泣けるとか、そういうのではないかもしれない。しかし、読み終えて、静かだが、確かで、深い余韻に包まれた。1989年にブッカー賞を受賞したという。それだけのことはある。見事な傑作である。以前読んだ「わたしを離さないで」も、とても良い作品だった。この作家はいつかノーベル文学賞をとるだろう。
「ノーベル文学賞をとるだろう」って、予言されている方がいました!
この作品は私も読みましたが、確かに読みやすい文章になっていました。ただ、淡々としているので、個人的な好みとしては、そこまで印象には残りませんでしたね・・(汗)
「充たされざる者」
原題:The Unconsoled
出版:1995年
あらすじ
この小説は、三日間の内に起こった出来事を書いたものだ。主人公は、有名なピアニストのライダー(名前)で、コンサートで演奏するために、中央ヨーロッパのとある街に到着したところである。
ところが、なぜか彼自身思い出せない、色々なアポイントメントや、約束事の網の中に絡めとられていく。そして、木曜日にあるコンサートの夜までに、それらの約束事をぜんぶ果たしておこうとするのである。事態を制御できない自分の無力さにさいなまれつつ。
読んだ人の感想
長すぎる夢、それも悪夢だ。つまらない。つまらない夢からいつまでも覚めない。悪夢だ。☆二つにしたのはつまらないからだが、再読したらつまらなくなくなるかもしれない。ふふふ…。
とてつもなくシュールな作品であった。読んでいて先が全く読めないし、それどころか今どこにいるのかすら分からなくなる。
この小説が凄いのは、それが比喩的なレベルを超えて、読んでいるこちらの頭の中までぐちゃぐちゃになってきてしまう辺りだと思う。(略)
これはやはりイシグロの圧倒的な筆力が成せる業なのだろう。細部は徹底的にリアルなのだが、文脈はたえず揺れ動き全体像ははっきりしない。でもぐいぐい読めてしまう。よく比較されるようにカフカや村上春樹に近いが、イシグロが頭ひとつ抜けていると思う。きっと、全体を貫く構成というか構想が強靭なのだ。
絵画や音楽にシュールなものが許されるのであれば、こんな小説もありかな。「何だこれは!」と思いながら、いつの間にかストーリーに引きずり込まれていき、先へ先へと読み進んでしまう。
読後感は?なんとも形容しがたい。ただ面白かった、というところか。ウィットに富んでいる。
カフカに似た、不条理な迷宮世界、というところで皆さんの感想は一致していました。なので、これは読む人によってかなり好みが分かれてきそうな作品だと思います。カフカとかベケットとか、カミュとか、不条理好きなアナタにはぴったりかも・・!
「わたしたちが孤児だったころ」
原題:When We Were Orphans
出版:2000年
あらすじ
主人公は、イギリス人男性のクリストファー・バンクス。彼は1900年代始めに、父母と一緒に上海租界に住んでいた。しかし10歳の時に、阿片商人であった父親が疾走し、続いて母親も行方不明になってしまった。そこでイギリスの叔母の元に引き取られる。
成長した彼は、腕利きの探偵になっていて、その手腕を活かして、両親をみずから探そうかと思っている。彼は、孤児の女の子を引き取って育てる。彼は1937年にふたたび中国の地を踏んだ。
彼が、今回の重要な任務を無事に解決したら、世界の破局が救えるのではないかという予感がある。だが、どのようにしてかは分からない。彼が捜査を進めるうち、次第に現実の人生と、幻想が混じり始める・・・。
彼は、日中戦争に巻き込まれる。年老いた探偵から教えられて、クリストファーは、両親が拘留されているかもしれない家屋の場所を見つけ出すことができた。もうすでに、四半世紀が過ぎているが、両親はまだそこに居るのではないかと、クリストファーは信じている。彼は負傷した日本兵と出会い、実はその兵士は幼馴染だったアキラではないかと思いながら、一緒に、家屋に入るが、そこには誰もいなかった。
次に、共産党のエージェントであるフィリップから、クリストファーの父親は新しい恋人ができて香港に逃げ、母親は中国人将兵に連れていかれたのだと聞かされる。そして、クリストファーがイギリスで学んでいた時の学費は、将兵の妻とさせられた母親が払っていたのだと明かされる。そして、クリストファーは1953年の香港で、やっと母親と再会することになる。しかし、母親は彼が誰だか分からないのだった・・・。
読んだ人の感想
始まりは青春小説のよう・・・
そして児童小説・・・
サラとの出会いは恋愛小説・・・
アキラとの再会からはシューティングゲームのよう・・・
不思議な小説です。
最後にぎゅっとまとめますが、少し置いて行かれたような気持になりました。
再読して納得しました
クリストファーは幼いころに行方不明になった両親を探すため私立探偵になるが、両親の行方を追って最後に明らかになった真実は彼の人生を根底から揺るがすものだった。『日の名残り』のスティーヴンスは、すべてを犠牲にして人生を捧げた仕事がその価値のあるものではなかったことに気づいた時、多いに泣いた。クリストファーも泣いたのだろう。しかし本作は、それが全く無価値ではなかったのだと肯定的に過去に向き合い、未来へのささやかな期待を抱く場面で終わる。切なく滑稽でグロテスクだが、最後はほんのり暖かい。不思議な作品だ。
飽きずに最後まで一気に読めたが、カズオ・イシグロではじめてイマイチだった。
バイアスのかかった語り手はいつものことだが、後半の展開がちょっと無茶になって、ストーリーそのものが信頼出来ない感じになってしまった。所謂「信頼出来ない語り手」の動揺、矛盾から読者なりの真実を探る面白みよりも、話のタガが外れすぎて、どこまで信じていいのか、疑心暗鬼になるのが先に来てしまうのだ。
特にいい加減な情報を元に、主人公が危険地帯に横柄な態度でズカズカ足を踏み込む後半は、これはスラップスティック・コメディ、ナンセン・ギャグなのか? と思ってしまうことも。
ちょっと異色の物語のようです。青春小説、子供向け冒険小説、コメディ、はたはナンセンスギャグ・・?まで思わせちゃうような、色々なエピソードが詰め込まれているようですね。これも、第二次世界大戦をモチーフにしているということで、戦争と、記憶の曖昧さというのが、ずっとカズオイシグロの大切なモチーフになっていることが分かります。
「わたしを離さないで」
原題:Never Let Me Go
出版:2005年
あらすじ
物語の語り部は、キャシー。彼女は自分のことを臓器提供者の「看護人」だと語り始める。もう12年間も、その仕事をしている。
回想の中では、よくヘールシャムという街が登場する。彼女はその街にある寄宿学校で子供時代を過ごしたのだった。そこでは先生たちは「守護者」と呼ばれていた。そして、生徒たちに授業を受けさせると共に、ずっと健康を保つように指示するのだった。その他、野菜を育てる菜園で働くことや、絵を描くことも推奨されていた。
しかし、ルーシーという一人の先生が、ある日こらえきれずに真相をばらしてしまう。この学校に集められた子供たちは、臓器を他の人間に提供するために作られたクローン人間なのだった。そして、数回の臓器提供ののち、まだ若いうちに彼らはその生を終えることになるのだと。ルーシー先生は、このせいで教育現場から追い出されてしまう。しかし真相を告げられても、奇妙にも従順に、子供たちは運命を受け入れ、特別に騒動が巻き起こったりはしないのだった。
やがて彼らは、もし本当に愛し合っているカップルだということが認められたら、そのカップルは臓器提供の時期を遅らせることが出来るのだと聞きつける。そして、自分たちが絵を描かされていたことも、それに関連するのではないかと考える・・・。
しかし、それは彼らの思い違いだった。ヘールシャムは、クローン人間をも、人間的に取り扱おうということで、実験的に開設された施設であり、絵を描かせたのは、外側の世界の人間たちに、彼らクローンにだって、創造性が宿っているんだということを見せるためだったというのだ。
読んだ人の感想
これは、私も読みました、よくイシグロカズオの代表作みたいに言われている衝撃作です。しかし、あらすじを読んでも分かるかと思いますが、とにかく悲しくて悲しくてやり切れない話でした・・・。
私の周りでも、結構この作品は絶賛する人が多いです。そして、あたかも本当のことのように、日常的な淡々とした口調で語られるので、「本当にあったことなの??」みたいに錯覚するような気分になると、けっこう皆言っています。
人によっては、今の時代を非常に思い起こさせてしまうと言っていました。原発もそうですし、誰かを犠牲にして、成り立っている社会というものを考えさせられてしまうわけです。
しかし、私には読むのが辛かった。うまく書けているだけに辛かったのかもしれません。特に、子供たちの従順さがツライです。なぜ、彼らはみすみす、自分たちが外側の世界の人間たちの犠牲にされているというのが分かっているのに、逃げないのか??暴動を起こしたりしないのか??この、従順さが非常に不気味と同時に、辛くてなりませんでした。
意外と、現実世界でも、例えば第二次世界大戦の時などに、若者が黙って兵士に取られていった・・もしかしてそういう従順さとも通じるのかもしれませんが、とにかく、読むのがきつかったですね・・・。
そして、カズオ・イシグロは、非常にエモーショナルなもので強力に読者を引っ張っていく作家だと思いました。ともかく、たんたんとした深い悲哀が全篇に満ちていました。わたしは、ちょっと悲しみ盛りすぎだろ!と思って耐えられがたかったです・・。
「夜想曲」
原題:Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall
出版:2009年
あらすじ
これは、カズオイシグロ初の短編集。5つの物語すべて、カズオも愛好する音楽に関係のあるものとなっている。
(1)クルーナー(Crooner)
クルーナーは、低い抑えた声で歌う歌手のこと。イタリアのヴェネチアが舞台。落ち目のアメリカ人歌手が、ポーランド人のカフェ・ミュージシャンを自分の仲間に誘う話。歌手は、ゴンドラの上から、心が通わなくなりつつある妻に向けてセレナーデを歌う。
(2)何が起こっても(Come Rain or Come Shine)
ロンドンに渡ってきた、外国人の英語教師が主人公。彼は大学時代知り合いだった夫婦の家に招かれるのだが、カップルの諍いが主人公にも影響し、奇妙なシチュエーションを招く。
(3)マルバーンの丘(Malvern Hills)
ロックでうまく身を立てられなかった若いギタリストが、ロンドンを離れ、姉妹と、その夫が営業するマルバーンの田舎のカフェへとたどり着く。そこでスイス人旅行者と出会い、自分が置かれている現在の状況について考えさせられることになる。
(4)夜想曲(Nocturne)
整形手術後、ビバリーヒルズのホテルで静養していたサックス演奏者が、リッチなアメリカ人女性と関わり合いになる。そして、ホテルの舞台の上で、奇妙な対決シーンを演じることになる。
(5)チェリスト(Celists)
ハンガリー人のセロ弾きが、自分にセロを教えてくれた年上のセロの達人に夢中になってしまう。そして、彼は、彼女が自分の音楽的才能を確信していて、どんな先生もそれには敵うはずもないと思っていたため、誰の教えも受けず、したがって、チェロを弾かないでいたのだということに気付く。
読んだ人の感想
作品の舞台が、ベネチア、ロンドン、モールバン、ハリウッド、アドリア海岸等で、勿論、音楽をテーマにしている。カズオ・イシグロ自身、ミュージシャンを目指していた時期があると公言しているだけに、音楽への造詣は深く、好みのジャンルも幅広く、その嗜好が作品を鮮やかに、艶やかに彩っている。長編小説においてはあまり表されることのない彼特有のユーモアのセンスが、この短編集においては遺憾なく発揮されているのも愉しい。
全体的に長編小説より肩の力が抜けた行書体の趣きがあって、こちらもまったく身構えずに読めました。
とくに「降っても晴れても」のユーモラスでナンセンスさがたまりません。最後の数節も大好きです。たまには眼の前の問題を直視したくないときだってあるし、先送りしたっていいじゃないか。そう思わせてくれる作品です。
何がテーマなのか 広告文(?)に惹かれて読んでみたが私の読解力ではテーマも何もわからなかった。
ただ、話があった それだけだった。
短編集ということで、肩の力を抜いてサラッと書かれたショートストーリー集のようです。長編小説に見られる、歴史や記憶など、重いテーマとの対峙はないので、気軽に読めそう。ただ、深さや重みを求める人には、物足りない可能性がありそうですね。
「忘れられた巨人」
原題:The Buried Giant
出版:2015年
あらすじ
小説の舞台は、アーサー王時代直後のイギリス。ブリトン人とサクソン人がそこには住んでいる。主人公たちが実際に目にすることは少ないものの、オーグルなど、幻想動物も存在する世界だ。
農村に住む、アクセルとベアトリスという、二人の老夫婦が主人公。二人は深い愛によって結ばれているのだが、村の中では、疎外されている。子供たちにからかわれたり、夜にロウソクを灯すことを禁止され、暗闇の中で過ごしていたり・・・。
アクセルは、ここの村人達の記憶に欠陥があることに気付いている。人々は、前に存在していた人や、一生懸命探したはずの行方不明になった子供などについて、すっかり忘れ去ってしまう。
ある日、ベアトリスは謎めいた浮浪者と出会い、近隣の村に、長く会っていない息子を探しに行くように駆り立てられる。許可をもらって、夫婦は出発。彼らは、息子は村の重要人物で、自分たち親に会いたがっているんだと、他人には説明するものの、実際のところ、息子についての記憶は曖昧だった・・。
読んだ人の感想
竜の息のせいで記憶をとどめておけない世界のお話。
竜の息で記憶を失ってしまうことが、幸せな思い出をとどめておけないと初めはネガティブなこととして描かれるが、実際は過去の諍いの記憶など対立の原因になる憎しみを忘れさせ結果として平和が保たれているということに気づかされる。
話自体はファンタジーの形式をとっているが、本質的には過去数年、連鎖的に起こる革命や過激派のテロの原因を暗示させるように感じました。
「日の名残り」、「わたしを離さないで」、「忘れられた巨人」の3作しか読んでいませんが、最新作である本作はもっとも単なるファンタジーと捉えられかねない描かれ方。いささか筋や設定にも無理があります。彼を初めて読む、象徴する作なら、まず、「わたしを離さないで」(never let me go)をおすすめします。
舞台は古代ですが、個人の中でぶつかり合う二つのアイデンティティ、「自分は何人か?」に基づく民族の記憶と「自分が愛しているのは誰か?」という個人の記憶の相克という近代的なテーマを扱っています。
(家族か国家かという選択をせまるところは、思いっきり現代のインテリジェンス小説と同じ構造なのですが、それをファンタジーでやっているところがすごい……)竜の吐息によって生じた霧で、人々の記憶にも靄がかかってしまう、という道具立てをすんなり受け入れさせてしまう設定も、全く見事だと思います。
ボンヤリした記憶をハッキリさせるために進む人々と、それを阻止しようとする人々……
やがてその対立が長年連れ添った夫婦の間にも訪れて……読み終わって、何日間も胸の裡に重い物を残していく物語でした。
ちなみに、私の感想はこちらの記事に書きました。個人的にはかなり好きでした!
ファンタジー形式なので、それが苦手な人にとっては、読みづらい可能性もあります。けれどイシグロの根本的テーマ「愛」「記憶」は、やはりこの小説でも貫かれていて、さらに、戦争や内紛、テロなど現代世界で巻き起こっている事態にも意識して書かれているようです。
「誰を愛するか」という個人の問題と、「どの集団(民族)に属するか」という集団の問題の葛藤についても描かれているようで、それが長年愛し合ってきた夫婦をも対立させてしまう、という結構シリアスなテーマですが、かなり興味深いものがあります。
まとめ: おすすめ作品をタイプ別に紹介
こんなわけで、カズオイシグロには短編小説集1つと、7作の長編があります。
おすすめとしては、
「とにかく代表作が読みたい!」「生命倫理や現代社会、生きることについて考えたい!」という人には
「私を離さないで」になると思います。
ただ、そうとう悲しい話なので、そこは覚悟してください・・・。
そして、カフカなど不条理な迷宮ものが好き、という人には
「充たされざる者」がいいかと思います。
悔恨と恋愛の、ほろ苦さを求める人、イギリス文化について知りたい人には、老執事の回想を描いた、もう一つの代表作「日の名残り」もおすすめです。
日本の近代史に興味がある、日本と戦争の関係についてもう一度考えたい、という人には「浮世の画家」は、一般人が戦争に協力していく心理について描かれているため、色々と示唆に富んでいるかと思います。
カズオイシグロの小説は、全体的に、とてもほろ苦く、洗練された味わいだと思います。よく引き合いに出されるような、村上春樹的な、華麗さはありませんが、渋く、ひたひたと感情を注ぎ込んでいく、そんな物語たちです。この機会に読んでみるのはいかがでしょうか。